【新宿本店3階 アカデミック・ラウンジ】中央大学法学部 連続講座企画 「ことばと正義」
【日時】
3月5日(水)・12日(水)・19日(水)・25日(火)
4月2日(水)・8日(火)
※ 第 回 月 日分は満席になりました
いずれも 18:30〜19:30
【場所】
紀伊國屋書店 新宿本店 3階アカデミック・ラウンジ
※ 着席のご予約はこちら
【このイベントについて】
「ことば」の大切さを法的な事柄を通して伝える連続講座です。
犯罪捜査において「ことば」が事件解決の鍵や証拠となったケース、口約束など契約の問題、誹謗中傷の問題、法廷通訳の問題、社会的弱者に対する情報保障など、身近なことから社会的課題まで、ことばの果たす役割について一緒に考えていきましょう。
第1回 3月5日(水) 「ことばと事件」小室夕里 中央大学法学部教授(応用言語学・辞書学) ※ 終了いたしました
ことばは正義をもたらすのか、はたまた不正義をもたらすのか。ことばの大切さと面白さを法的な事柄を通して考えていく連続講座の第1回です。ことばを巧みに用いて相手を操る犯罪や、ことば言語学の知見が実際の事件の解決において役割を果たした事例(自白の強要、遺書・いやがらせメールの書き手の特定など)を紹介します。
第2回 3月12日(水)「ことばと暴力」谷井悟司 中央大学法学部准教授(刑法) ※ 終了いたしました
「ことば」とは薬にも毒にもなるもので、使い方を間違えれば、誰かを傷つけ、死に追いやることもあります。ソーシャルメディアの普及は、否応なくこのことを痛感させました。インターネット上の誹謗中傷(オンラインハラスメント)が社会問題となった今、その抑止・対策を求める声が法律、とりわけ、刑法に強く寄せられています。それでは、こうした「ことば」の暴力の問題に対して、刑法はどのように向き合うべきなのでしょうか。
第3回 3月19日(水)「ことばと約束」森光 中央大学法学部教授(ローマ法) ※ 終了いたしました
契約は「ことば」を使ってなされる。書いたことばや発した「ことば」に強制力がともなうことになる。しかし、しばしば「ことば」は多義的である。ある「ことば」の意味が一義的に確定できないとき裁判はどのようになされるのであろうか。
第4回 3月25日(火)「ことばと裁判」北井辰弥 中央大学法学部教授(英米法) ※ 終了いたしました
古代日本では守るべき規範のことを「のり」といいました。これは祝詞(のりと)にも通じます。ことばがなければ法もなかったのです。裁判はことばで行いますから、西洋でもことばにまつわる伝承は豊富です。裁判で自白がとても重視されることとも関係がありそうです。でも法廷でことばが通じない場合はどうなるのでしょうか。古代の法の源流から現代の法廷通訳の現状まで、ことばと裁判について考えてみましょう。
第5回 4月2日(水)「ことばと労働」井川志郎 中央大学法学部教授(労働法) ※ 終了いたしました
働く場での「ことば」の問題といえば、それが行き過ぎて相手を傷つける(パワハラ、いじめなど)、というものがイメージされるかもしれません。しかし逆に、「ことば」が不十分だと困ってしまう人も出てきます。それは、私たちの自由・平等や健康・生命にも関わってきます。具体的には、どのような問題があるのでしょうか。そして、法ないし法学は、その解決に役立つのでしょうか。
第6回 4月8日(火)「ことばと権利」小田格 中央大学法学部准教授(社会言語学)
ことばで困ったことがありますか。海外旅行の際であれば、その場はつらくとも、後に振り返れば良い思い出になるかもしれませんが、それが災害時であったらどうでしょうか。すべての人に情報を保障するということから、ことばと権利について考えてみましょう。
ファシリテーター:小室夕里 中央大学法学部教授(第1〜6回)
言語学の視点からの解説:中村文紀 中央大学法学部准教授(言語学)(第1〜6回)
中央大学のイベントHPはこちら
【参加方法】
無料でご観覧いただけるイベントです。
◇着席でのご参加:事前にご予約をお願い致します。(先着26名)
☆申込から参加の手順☆
①下記ページにて「参加申込(着席分)」を申し込む。
②イベント当日、新宿本店3階アカデミック・ラウンジにて、受付にてお名前をお知らせ下さい。
予約フォームはこちらから ※ 第 回 4月 日分は満席になりました
◇予約なしのご参加
オープンスペースでの開催となりますので、ご予約なしのお客様も立ち見にてご観覧いただけます。
【登壇者プロフィール】

小室 夕里 (こむろ・ゆり) 第1回
中央大学法学部教授。英国エクセター大学で辞書学を学ぶ。専門は英語辞書学。『コンパスローズ英和辞典』(2018)や『ライトハウス英和辞典』第7版(2023)などの学習英和辞典に執筆者として携わる。英和辞典の編纂に携わる人々へのインタヴューを「英和辞典の作り手たち」(https://ej-lexicographers.com/)に掲載中。

谷井 悟司 (たにい・さとし) 第2回
中央大学法学部准教授。博士(法学)。東京都立大学法学部助教、中央大学法学部助教を経て、2024年4月より現職。専門は刑法。主に刑事過失論を研究。主要論文として、「すり替え型キャッシュカード窃盗における実行の着手時期」法学新報129巻6・7号(2023年)493頁、「医療過誤における刑事過失責任の明確化」年報医事法学38号(2023年)9頁、「福島第一原発事故刑事裁判の点検――避難者国賠訴訟最高裁判決および株主代表訴訟第一審判決を手掛かりとして――」法学新報130巻7・8号(2024年)37頁など。

森 光 (もり・ひかる) 第3回
中央大学法学部教授。中央大学通信教育部長。中央大学法学部助手、助教授をへて2017年より現職。
専門はローマ法。主要著書として『ローマの法学と居住の保護』(日本比較法研究所、2017年)がある。この他、法律学への入門に関して、『法学入門』(共編著、中央経済社、2023年)、『法学部生のための法解釈学教室』(中央経済社、2023年)、『法学部生のための小論文教室』(共編著、中央経済社、2023年)がある。

北井 辰弥 (きたい・たつや) 第4回
中央大学法学部教授。日本比較法研究所長。桐蔭横浜大学法学部助教授、中央大学法学部准教授を経て2014年4月より現職。専門は英米法。主に英米契約法と明治期日本への英米法の受容について研究。「ことば」に関する著作として、「イギリス契約法におけるコンセンサス」津野義堂編『コンセンサスの法理』(2007年)、「権利と権理についての一考察―幕末・明治初期の外交文書を手がかりとして」日本比較法研究所編 『Future of Comparative Study in Law』(2011年)など。
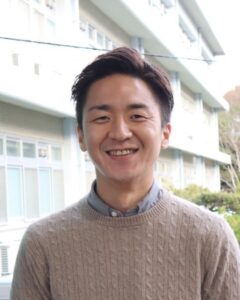
井川 志郎 (いかわ・しろう) 第5回
中央大学法学部教授。独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタントフェロー、山口大学経済学部講師、同准教授を経て、2023年4月より現職。専門は労働法。主に国際労働問題に関する法的規律のあり方を研究。主たる著作として、『EU経済統合における労働法の課題~国際的経済活動の自由との相克とその調整』(旬報社、2019年)、「プラットフォーム就労と法適用通則法12条」日本労働法学会誌135号(2022年)69頁、「『ビジネスと人権』と労働法」労働法律旬報2071・72号(2025年)6頁など。

小田 格 (おだ・いたる) 第6回
中央大学法学部准教授。中央大学法学部卒、同大学文学研究科中国言語文化専攻修士課程、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。公益財団法人大学基準協会評価事業部評価第2課課長などを経て、2020年4月から中央大学法学部に着任。専門は中国語圏の言語政策・言語法。

中村 文紀 (なかむら・ふみのり)
中央大学法学部准教授。博士(文学)。北里大学一般教育部専任講師、中央大学法学部助教を経て、2023年4月より現職。専門は、言語学・言語学。主に現代英語の通時的変化を研究。主要論文として、「補文標識likeとthatの競合における多層的動機付け: 言語変化における革新と伝播の観点から」『新しい認知言語学 言語の理想化からの脱却を目指して』(2024年、ひつじ書房)111-131頁、「連結詞的知覚動詞構文の談話標識化:現代アメリカ英語における調査」『語法と理論との接続をめざして : 英語の通時的・共時的広がりから考える17の論考』(2021年、ひつじ書房)343―363頁、「法学と言語学の接点としての商標言語学:「エスカレータ」の普通名称化を例に」北里大学一般教育部紀要第25号(2020年、五所万実氏との共著)1−20頁など
(紀伊國屋書店 新宿本店・アカデミックラウンジ事務局)